皆様、こんにちは。
本日はタイトル通り、部下育成に悩んでいる方に向けた記事になります。
よく名選手、名監督にあらずなんて言葉を耳にしますが、指導や育成ってこの世の中で一番難しい分野だと思います。
理由は人の心理が関わっているから。いわゆる心理学が作用しているため、上司のこうすべきという指導に対して、素直に従わない場合も現場ではよくあることだと思います。
私は介護老人保健施設のリハビリ科にて主任を5年務めていました。もちろん最初は全くといっていいほどうまくいきませんでしたが、学んで実践して学んで実践してを繰り返すうちに、マネジメント能力は身に付いてきたと実感しています。
私の経験談をお話ししますと、うまくいってなかった時は、
『指導が押し付け』
になってしまっていました。
つまり、「こうしなさい」「こうあるべき」という上からの指導になってしまっていたんです。当時を振り返ると、それが正しい指導だという認識でした。
管理職を任される立場にある方は、いちプレイヤーとして認められた結果、昇進するケースがほとんだと思います。つまりプレイヤーとして結果を残せたイコール仕事のやり方も正しいという認識の下で部下と関わっていくものだと思います。
ところがどっこい( ;∀;)
セロリの歌詞にあるように
【育ってきた環境が違うから~♪好き嫌いは否めない~♪】
なんです( ;∀;)
今、現在進行形で部下育成に悩まれている方は、次のような心の持ち方で部下と関わるとよいかと思います。それは、
1 すぐに結果を求めない
2 笑顔で挨拶する
です。
「あれ、指導論じゃないんかい!」って思われた方もいるでしょうが、実は心の持ち方で全然違った世界になります。
ただ、勘違いしてほしくないのは、例えば仕事をサボっていた部下がいたとしても、それを容認するような放置的な指導を言っているのではありません。もちろん遅刻等はいけませんので、注意するときは注意するというスタンスは必要です。
部下指導において、悩みはどこからやって来ると思いますか?
少し考えてみてください。
私が思うに、
上司の理想と部下の現状の能力とのギャップからくるもの
だと思います。
お給料もらってるんだからこれくらい勉強したり、スキルを身につけたりするのは当然でしょうという上司自身の考え方が、部下との心の距離を遠のいてしまっている可能性が高いです。そのため、指導したことが今一つ部下に響いていなかったりと、暖簾に腕押し状態を経験した管理職の方は多いのではと思います。
これをスポーツの現場で置き換えると、監督と選手間でもよく起こることだと思います。監督が要求するプレーと選手の現状のプレーとのギャップが大きければ、そこに亀裂が生じてしまいます。地区大会1回戦負けのチームにいきなり全国強豪校の監督が就任してきたら、どうでしょう。選手はそこまで上手くなることを求めていないのに、監督は一生懸命に指導にあった場合、ギャップが生まれますよね。心の根っこの部分を指導して、選手の間で、もっと上手くなりたい、勝ちたいという願望が出てこないと、結果を出すのは難しいと感じています。強豪校の練習では当たり前の練習量を1回戦負けレベルのチームが行ったら、選手からパワハラと認定されてしまうこともあるかと思います。時代的に。
スポーツの現場を例えに使いましたが、監督の思いとは裏腹なことが起こってしまうのです。監督の思いに対して選手が付いてこなかったら、選手からパワハラ扱いされてしまうのは、避けたいことです。
じゃあどないしたらええねんってなりますけど、
先に挙げた、すぐに結果をもとめないことと、笑顔で挨拶を実践すると良いです。
理由は、温かい人間関係を構築できるからです。そうすると、部下から自己開示してくれたり、色々な変化が起きます。土台に良好な人間関係を構築することが重要なのです。その上で、部下と話し合いの場を設けます。
そこで確認することは、
なぜ、この仕事を選んだのか
今後どうなっていきたいのか
という部下の願望を聞き出すことです。
スポーツの例を挙げましたが、選手がどうしたいのかという願望がないと監督の指導が暖簾に腕押しとなります。
したがって、部下の求めていることにフォーカスしてあげて、上司は最大限フォローに回る関わり方をすると良いでしょう(^^♪
私が主任をしていた時、うれしかったことがあります。
それは、メンバーが9人いるうちの4人が結婚したことです。仕事のストレスを重度に感じていたら、プライベートも充実しません。そんな中で、プライベートでうれしい、ハッピーなことがたくさんあったのは、管理者冥利に尽きます☆
◇まとめ
最後に、
大事なことは、結果をすぐに求めない心の在り方を定着させ、部下の願望実現に貢献するような関わり方を目指していくと、良い環境、良い現象が生まれるでしょう。
私は主任就任当初は、メラメラ燃えすぎていました。結果が欲しかったからです。よくしたかったです。
しかし、それでは部下とのギャップが生まれてしまいます。
今回お伝えしたのは、私の苦い失敗から学んだ教訓です。
同じように部下育成、マネジメントで悩まれている方の希望になれればと思っています。
すぐに結果を求めず、コツコツコツコツとお互い成長していきましょう(^^♪
期待しています☆
本日も最後まで読んでくださり、ありがとうございました。
本日の格言
すぐに結果を求めない

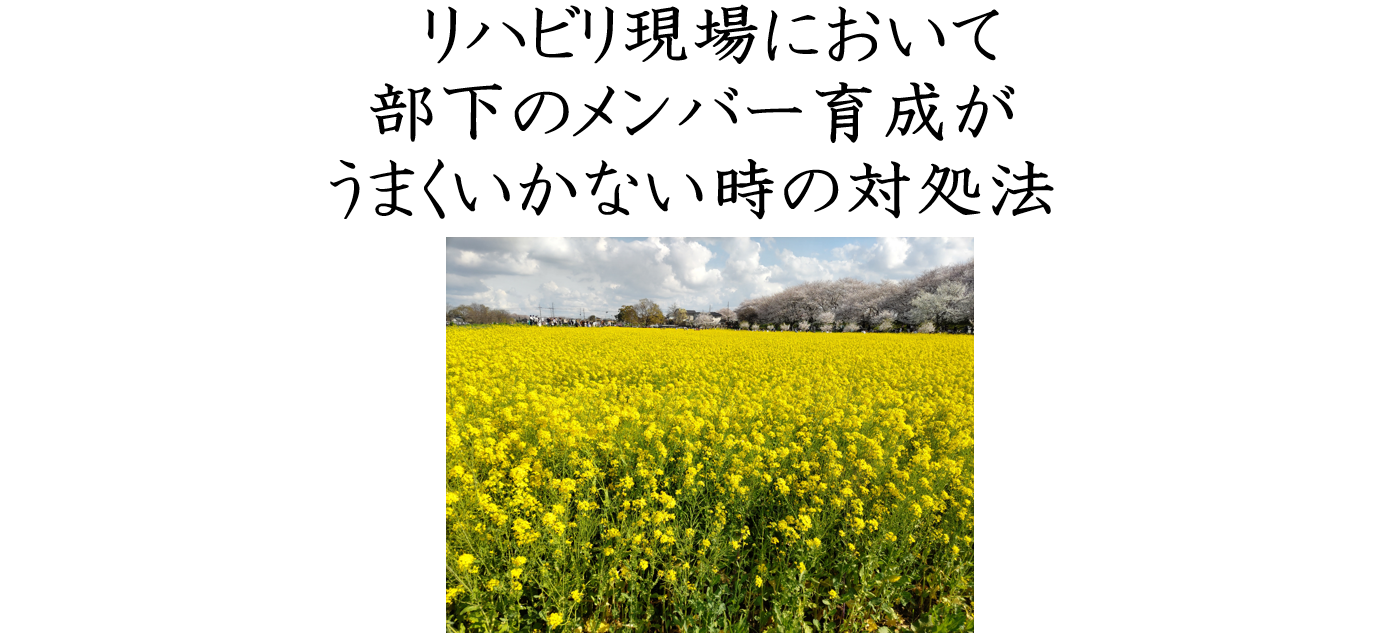
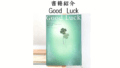

コメント