皆様こんにちは。
今回は部下とリハビリ診療を併診する時の教育法についてお伝えしたいと思います。リハビリの現場では、なかなか忙しく、部下と併診して育成するという機会は少ない印象を受けます。
そんな中でも併診は、とても効果的な教育法であるため、今回ポイントをお伝えしたいと思います。
◇併診のメリットとは
私が思うメリットは以下に要約できます。
患者様の反応を分かち合えるまさにリアル臨床を経験させることができる。筋促通後の動き、運動後の循環動態とその評価など、リアルタイムで起こっていることの意味付けを伝えることができる。
です。
経験談をお話しすると、重度の膝関節症の患者様でリハビリの方向性に迷っている部下がいました。その患者様は理解力不足や難聴もあったため、スムーズに進められない難しさがありました。その患者様を併診して、私がやったことは『評価』ですね。
どこが痛いのか?
何が痛いのか?
何をすると痛いのか?
重症度的にどうか?
移乗やトイレ動作時の痛みはどうか?
促通してどれほど改善されるか?
という至ってシンプルなことを診て、部下と意味づけをして、方向性を話し合いました。結果的に痛みも軽減され、車いす移動から歩行車に拡大することができました。
大切なのは、
・いかに評価した内容に確信がもてるか
・併診することで部下の思考の幅を拡張できるか
この2点です。
さらに重要なことをいうと、特別なことは一切なく、ただただ普段のリハビリ診療そのままを上司がみせることができるかが重要です。評価もせず、なんとなくの診療、なんとなくの可動域訓練では成長はありません。普段から部下の担当患者様にも目を配り、自分の担当だと思って仕事をする意識が大切なのではないかと思います。
上記の体験談は部下が相談してくれたことも重要です。部下が全く方向性も定まらないまま日々リハビリをしていたらどういうことが予測されるでしょうか?
そうです。患者様はよくならず、車いすのままだったわけです。
上司が代わって単独でその患者様を診療するのもひとつの手かもしれません。でもそれでは部下が育たないんですね。上司は管理業務もありますから忙しい中、そうした併診の機会を作り、患者様を通して、何を教育していくのかを見定めることが、結果的に組織の発展につながっていくのです。
そうした上司の熱心な取り組みは長期的にみてもメリットがあります。
◇併診の長期的なメリット
それはその教育した部下が後輩の指導を同じように行ってくれます。組織に教える、教わるの文化ができたらどうでしょう。とても強い組織に生まれ変わります。私は最初の3年こそひとりひとり教育していきましたが、ある程度部下が育ってきたら、その部下たちが後輩の指導を担っていたので、結果的に自身の業務に集中できる仕組みを作ることができました。
患者様の問題点
患者様の方向性
患者様の予後予測
こうした基礎基本を明確にしていく訓練を積ませていけば、組織の中の共通言語ができますし、的外れな報告をしてくる部下はいなくなります。上に挙げた問題点、方向性、予後予測は新人でも大事な要素ということは分かっています。でも実際に患者様を通して、部下に伝え、指導しないと本当の意味での理解にはつながらないことは、肝に銘じておくと良いでしょう。
◇まとめ
併診というのは、一番はリアル臨床であること。
上司の一番の見せ場!!
その場で評価をし、問題点を抽出し、治療して変化を出す一連の流れをやってみせないと、正直意味がありません。
山本五十六さんの名言に「やってみせ、言って聞かせて、させてみせ、ほめてやらねば、人は動かじ」とありますが、まさにこれだなと思います。教育的立場にある管理職がなにより一番に成長を求める組織って、素晴らしい組織だと思います。しかし、きれいごとだけではありません。成長とは変化ですから、その変化を嫌う社員も少なからずいるはずです。「どうして勉強会に参加しないといけないの?」とか「これ以上忙しくなるのは無理です」という社員もいます。そこは正直無理に変えようとしなくていいです。自身が正しいと思うこと、つまり、医学の勉強、コーチングのための心理学の勉強、部下へのフィードバック、自身の診療の振り返りなどなど自分が正しいと思う道を歩めば、必ずみてくれる人が現れます。
ウサギとカメの昔話のように、カメのようにゴールを見続ければ良いのです(^^♪
精神的な強さも必要になってくるかと思いますが、それも自身の成長につながります。
共に頑張っていきましょう♪
本日の格言
「やってみせ、言って聞かせて、させてみせ、ほめてやらねば、人は動かじ」
By 山本五十六


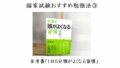
コメント