皆様こんにちは。
今回は優秀な社員を部下に持った時の指導のコツについてお話します(^^)
普通はやや問題を抱えた社員についての関わり方というアドバイス的な内容のものが多いですが、今回は視点を変えて即戦力に値する社員が入ってきた時の心の持ち方についてお伝えします。
伝えたいことは次の3つです。
1 優秀な社員にはバランス型と突出型がいる
2 優秀な社員は、リーダーの力量を測っていることを自覚して、自分を高めていかなければならない
3 優秀かどうかは実は事実ではない。優秀かどうかを決めるのはリーダー自身の考え方で決まる
まず1の優秀な社員にはバランス型と突出型がいるについて説明します。バランス型というのは、知識・技術・接遇面・協調性において平均点以上の人財と置き換えることができます。突出型というのは、ある特定の分野においての知識や技術が卓越している反面、接遇面・協調性はもう少しというようなタイプの人財です。両タイプも優秀には変わりないのですが、突出型のタイプは短所が出てしまう傾向があるため、指導においてはリーダーの役割が非常に重要になってきます。良き理解者にならないと、短所だけが浮き彫りになってしまい、所属する組織にも居づらくなってしまうため、社員がみているところで長所を褒めたりして、良い印象を与えられるように配慮すると、組織がものすごく活性化されていきます。
次に2の優秀な社員は、リーダーの力量を測っていることを自覚して、自分を高めていかなければならないについては、その通りです。リーダーは常に2歩3歩先をいっていなければいけないと考えます。そうすると、部下からの相談事に対して、的確に指示がだせることや、端的に伝える力は常に鍛えておく必要があります。部下からの相談事に対して曖昧に返答したり、忙しいを理由に雑に対応してしまうと黄色信号ですね。なぜなら優秀な社員は成長欲もあるため、見切りをつけられてしまう恐れもあるからです。めちゃプレッシャーなんです。
でもこれは非常にプラスになると考えていて、ひとつひとつの対応が試されているということは、自分に対しての危機感にしていけばいいと考えます。つまり、お互いが成長し合える存在になったら、素晴らしい組織が出来上がるということです。よって、社員が優秀だからといって、それに甘えず、絶えず自身に負荷をかけていくとよいのです。
最後に3の優秀かどうかは実は事実ではない。優秀かどうかを決めるのはリーダー自身の考え方で決まるというのは、深い学びです。言葉で理解するのは難しいですが、それを裏付けるものがあります。
それは私がコーチングを学んでいく中で出会った『望めば叶う』という本(ルー・タイス 著)に書いてある一節の中にヒントがあります。以下紹介したいと思います。
【いまでは古典となったある実験では、教師たちに、クラスのどの子どもに才能があり、どの子どもは「学習能力が低い」かが伝えられた。実際には、どの子どもの能力も似たようなもので、才能ある子とない子の区分けも無作為に行われた。ところが、一学年が終了するころには、子どもたちの成績が教師の見方を反映していたばかりでなく、知能指数まで、教師の固定概念にしたがって上がったり下がったりしたのである。】「望めば叶う」ルー・タイス著 日経BP(P86)
お分かりいただけたでしょうか?
子どもたちの成績が教師の見方を反映していたというは、実験ではありますが、とても興味深い情報です。
私はやはり優秀である、優秀でないというのは、リーダーの心の在り方によって決まるものだと思っています。でもこうして学ぶものもおもしろいですよね(^^♪
◇まとめ
今回は優秀な社員を部下に持った時に指導のコツについてお伝えしました。いかがでしたでしょうか(^^♪
特に今回はルー・タイスさんの著書の中の言葉を引用させて頂きましたけど、興味深い内容だったと思います。
結局は指導する側の心の状態が左右する
ということだと思います。(断定できないのはまだまだ深められる伸びしろがあるということです!)
私はこうしたマネジメントやコーチングに関する分野を勉強するのはとても楽しいです。
何かひとつでも読者の皆様のお役に立てれば幸いです。
本日も最後まで読んでくださり、ありがとうございました。
本日の格言
育成とは、結局は指導する立場の心の在り方で決まる
今回引用させて頂いた書籍
『望めば叶う』 ルー・タイス 著 吉田利子 訳
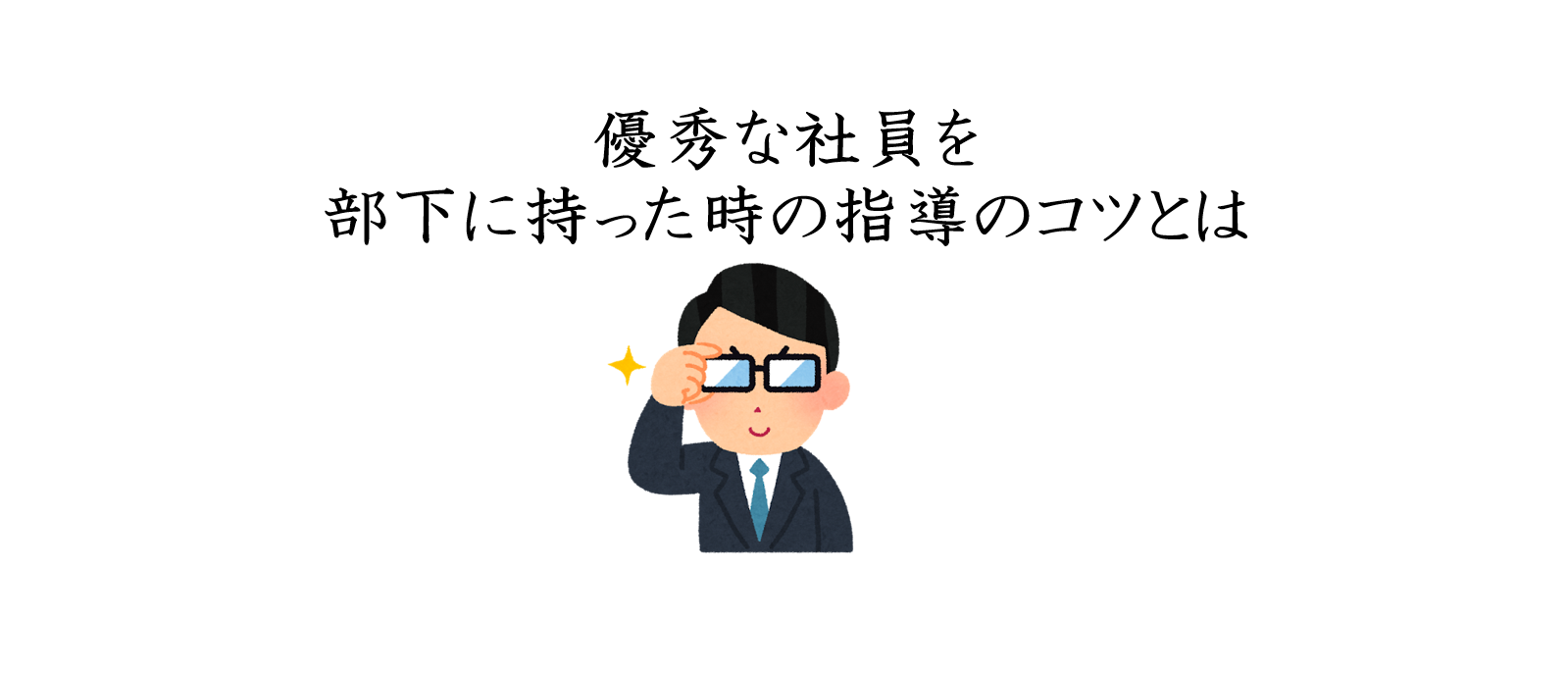

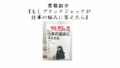
コメント