この記事はタイトルの通り、臨床実習生や新人理学療法士の方に向けて発信しています。
その他〇〇編と称した他のシリーズもあるので、気になった方は参考にして頂けると幸いです☆
さて、今回は疾患と障害をつなげるコツについて述べたいと思います。
新人育成において短期的な目標に置かれるのが、「情報収集」「リスク管理」「病態の理解」ではないかと思います。
自動車の運転に例えると、走行前のブレーキの確認やミラー確認、シートベルトを締めるという確認作業を教習所で教わると思いますが、それと医療現場は一緒だと思います。では、医療現場においてミラー確認やシートベルトを締める作業は何に置き換えられるか?
やはりそれは「情報収集」と「リスク管理」ではないかと思います。
その両者を正しく理解する上で必要になってくるのが、「病態の理解」です。
このワードを聞いて、難しいなと思う人は多いと思います。なおかつ副題にある「疾患と障害をつなげる」ってさらに複雑なんじゃないかとネガティブな感情を抱く人は少なくないはずです。
だからこそ知っておかなければならないことだと思いますし、今回はそのコツをお伝えします。
疾患と障害をつなげるポイント3つ!!
ポイントは以下の3つです。
1 各疾患の病態的特徴を理解する(疾患あるあるみたいなものの把握)
2 ADLを細分化して、問題点を抽出する
3 細分化し、統合と解釈を経て、プログラムに反映させる
です☆
脳卒中片麻痺を例にして説明していきます。
まず片麻痺の病態の特徴として、錐体路障害による深部腱反射亢進、病的反射の出現、筋緊張の異常、姿勢反射障害などが挙げられます。
つぎにADLの細分化については、排泄動作を例にして説明します。
排泄動作を細分化するとどんな要素が含まれていますか?
考えてみましょう!
◇トイレの出入りの移動
◇方向転換
◇下衣類の操作
◇便座への着座・起立
◇便座での座位保持
◇後始末
などがあります。
こう細分化して、考えてほしいのが、担当の患者様はどこに介助を要しているのか?という動作観察からの動作分析をしてほしいのです。
起立場面なのか?
下衣類の操作なのか?
方向転換時なのか?
指示理解の曖昧さなのか?
動作手順の遂行能力の低下なのか?
ここがポイントですかね。なぜなら、ここの部分を分析することで、問題点の抽出からの治療プログラムが変わってくるからです。
この点が明確になってくると、再評価を繰り返してより問題点抽出の精度が上がり、プログラムの意味づけが濃くなってくるということです。
例えば患者様に立位保持練習・立位での重心移動練習をしている先輩セラピストがいるとして、その先輩にその練習を行っている理由を聞いた時に、
A先輩『この患者様は在宅復帰にあたっては、トイレ動作の自立が必須の方でトイレ動作の自立を目指しているよ。それで現状は下衣類の操作に介助が必要な方なのね。その原因として立位保持がフリーハンドで20秒未満でファンクショナルリーチテストもカットオフ値に満たしていないため、まずは立位バランス能力の向上を目標に行っているよ。あと麻痺側への重心移動の際に、身体を制御できなくてバランスを崩す場面もあるから、麻痺側下肢の支持性も向上させていく必要があると考えている。麻痺のレベルも軽度なことや認知機能はクリアな方なので、筋促通や動作練習を繰り返すことで、動作学習が図られ、能力の獲得は十分見込めると考えているよ。』
と返答があったら、納得いくと思います。
この先輩は排泄動作の下衣類操作に着目してアプローチしていることが分かると思います。
さらに下衣類操作を細分化すると、立位保持、立位保持状態での重心移動、例には挙げませんでしたが、プラスアルファでリハビリパンツ(パッド含む)の操作、麻痺側上肢のズボンの操作などがあります。あとは、排泄動作の一連の動作理解のための認知機能の評価や片麻痺であれば半側空間無視などの高次脳機能の評価も大切な要素になってくるかと思います。
挙げれば挙げるほど複雑にはなってしまいますが、このように病態からの障害、現状の姿勢・動作観察と分析、からの問題点抽出→目標の設定→治療プラグラムの立案と実践という流れになっていきます。
どうでしょう?イメージできましたか(^^♪
まとめ
では、まとめにはいります。
1 ADLの中で介助を要している場面を把握する
2 なぜ介助を要しているかをADLの細分化と病態の特徴を結び付けた統合と解釈を行う
3 問題点抽出と目標設定、プログラムの立案をしていく
この3段階を踏めば、まず大きく外れることはないです。
そうすれば、普段の診療がより濃くなると思いますし、楽しくなります(^^)/
ぜひ、参考にして頂ければと思います。
最後にすごく今回のテーマ沿った参考書籍を2冊紹介したいと思いますので、気になった方はぜひ手に取って勉強してください☆
おすすめ書籍①
生活機能障害別・ケースで学ぶ 理学療法臨床思考 ~自立支援に向けて~
嶋田智明 (編)
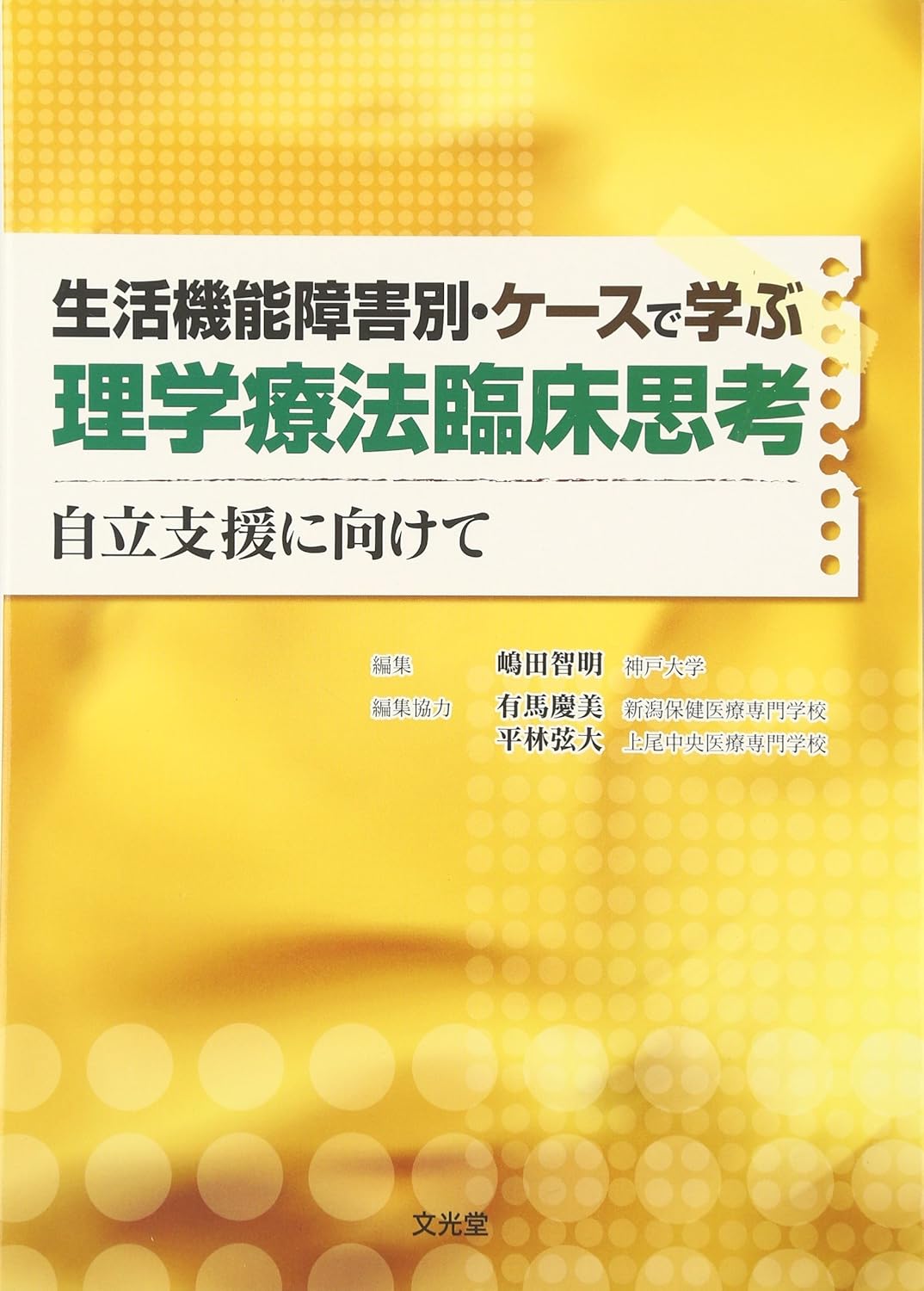
おすすめポイント:一言でいうと生活動作とはが簡潔に学べる一冊です。食事、排泄、更衣動作などの生活動作の障害からの片麻痺やパーキンソン病、大腿骨頸部骨折などの各疾患の症例から、どのように臨床推論を進めていくかが丁寧に解説されています。特に回復期病院や老健に勤めているセラピストにおすすめです☆
おすすめ書籍②
『症候障害学序説~理学療法の臨床思考過程モデル~』
内山 靖 著
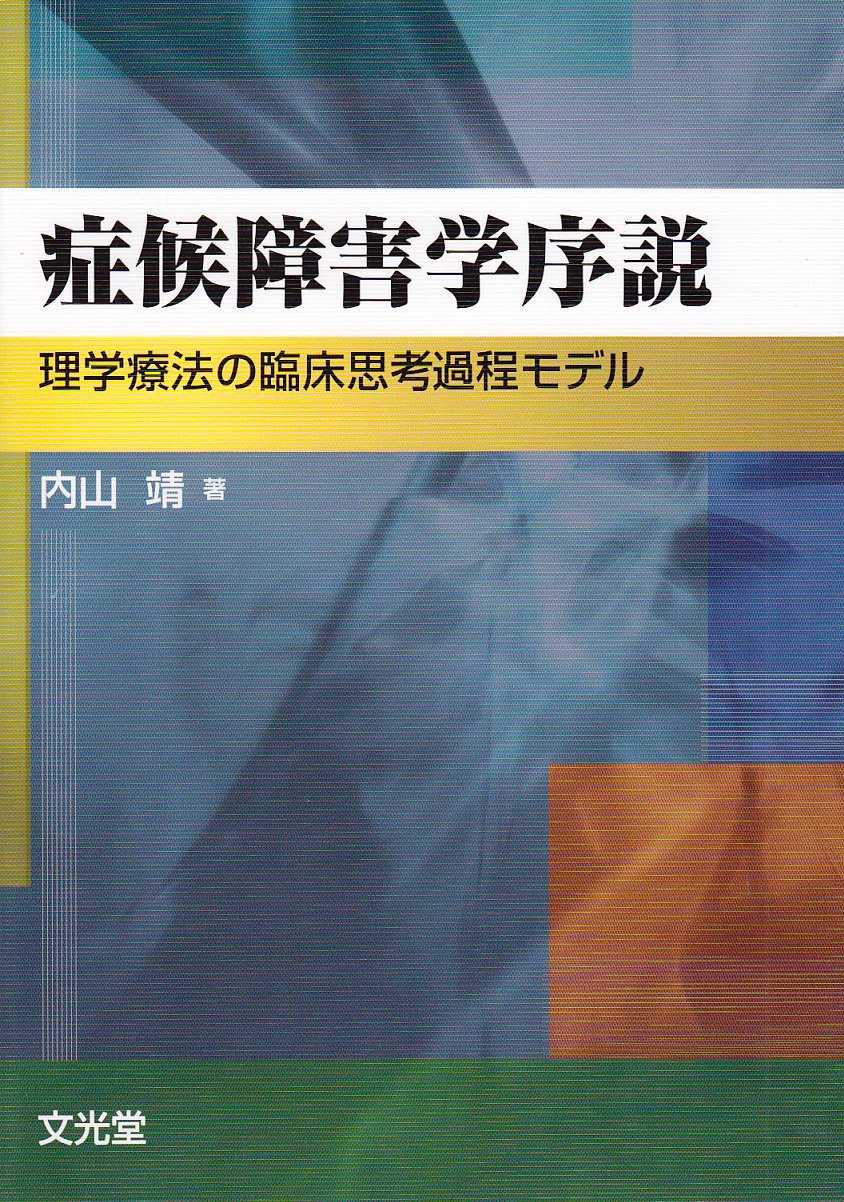
おすすめポイント:一言でいうと臨床においての深く掘り下げる作業の基礎が学べる一冊です。目の前の患者様の症候や障害をどう捉えて、プログラムにつなげていくのかを学べます。分かりやすいビジュアル(図)が豊富なため、とても学びやすい一冊となっています☆
本日も最後まで読んでくださりありがとうございました(^^)/
本日の格言
成長につながる診療とは過程を大事にしていくこと
他のシリーズもありますので、併せて読んで頂けると幸いです(^^)/
臨床実習生や新人理学療法士が押さえておきたいこと~心構え編~
臨床実習生や新人理学療法士が押さえておきたいこと~キャリアデザイン編~
臨床実習生や新人理学療法士が押さえておきたいこと~クリニカルリーズニング編~
臨床実習生や新人理学療法士が押さえておきたいこと~情報収集編~
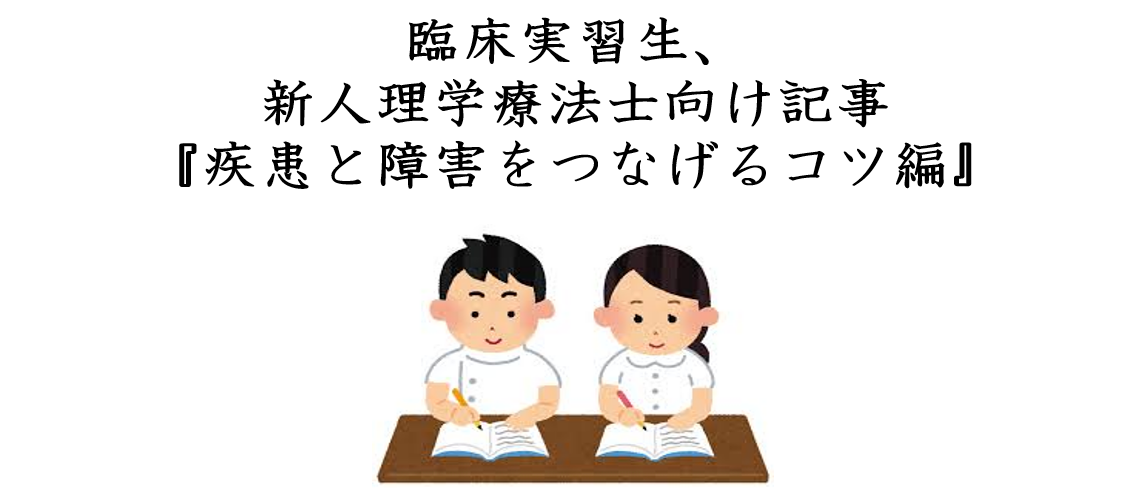
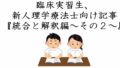

コメント