この記事はタイトルの通り、臨床実習生や新人理学療法士の方に向けて発信しています。
その他〇〇編と称した他のシリーズもあるので、気になった方は参考にして頂けると幸いです☆
さて、今回は統合と解釈編です。
これは大多数が壁にぶち当たることではないでしょうか?
私もこれを指導するときは、どう理解してもらおうか多く悩んだ経験があります。
しかし、次のポイントを押さえることで、理解につながると思いますので、ぜひ参考にしてください。
1 まず、大前提として統合と解釈とはについて調べる
2 極端な例を用いて、理解を深めていく
3 SOAP形式のカルテを書き、Aの部分を濃くするトレーニングを意識的にする
です。
1の『統合と解釈とは』という定義については検索すれば出てくると思いますので、ぜひ皆さん調べてみてください。まずは定義を押さえることが大事です☆
私が捉える統合と解釈を一言でいえば、
評価と問題点抽出をつなぐ架け橋
(※個人の見解を含む)
です。
つまり、統合と解釈なくして問題点抽出にはたどり着けないということです。
これを知っただけでもとても視野が広がると思います。
次の2の極端な例を用いて理解を深めていくというのは、評価とプログラムの関係を紐解くと良いです。
例えば、
評価項目:関節可動域はNP
↓
問題点:#.関節可動域制限
↓
プログラム:関節可動域練習
これは整合性が、、、
ない(→が成り立たない)
のはお分かり頂けると思います。可動域制限ないのに可動域のプログラム立案は整合性はありません。
次に
評価項目:筋力MMT2
↓
問題点:#.筋力低下
↓
プログラム:筋力練習
これは整合性があります。極端な例ですけどね(^^♪
でもこうして極端に考えると自分自身にフィードバックが起こります。それだけ統合と解釈を理解するというのは難しいもので、ひとつひとつ噛み砕いて情報を整理していかねばなりません。
実際の現場でも統合と解釈のずれが生じている例①のような誤りが出てしまうときがあるかと思います。
だから、統合と解釈の能力というのはとても臨床の現場では求められてくるのです。
最後に3のSOAP形式のカルテを書き、Aの部分を濃くするトレーニングを意識的にするについては苦手としている人は多いのではないでしょうか?私は若手時代は、先輩のカルテを見て、パクっていましたね。「なるほど、こう表現したいときはこう書けば良いのか!!」などの発見が多々ありましたので。
このトレーニングを通して気付いてほしいのは、
SとOができてないとAがしっかり書けない
つまりPまで到達しない
ということです。
ということは、やはり情報収集と評価がめちゃくちゃ大切となります。
最後に、私見になりますが、
料理もそうで、ラッキーパンチでおいしくできた時と
色々と試行錯誤してできた時だと
どちらが成長できるでしょうか?
よりおいしさの再現性があるのはどちらでしょうか?
後者の試行錯誤を経ることですよね☆

日々の忙しい中だと、流れ作業になってしまうこともあるかと思います。しかし、学生や新人時代の努力というのは未来永劫の財産になりますから、
今しかできない学びを追い求めていってほしいと思います。試行錯誤してこそです。
先輩・上司にたくさん質問を投げかけてみましょう(^^♪
私もまだまだまだ道半ば
共に成長していきましょう(^^♪
本日も最後まで読んでくださりありがとうございました。
今日の格言
本気で診た1症例は、必ず自分の財産になる
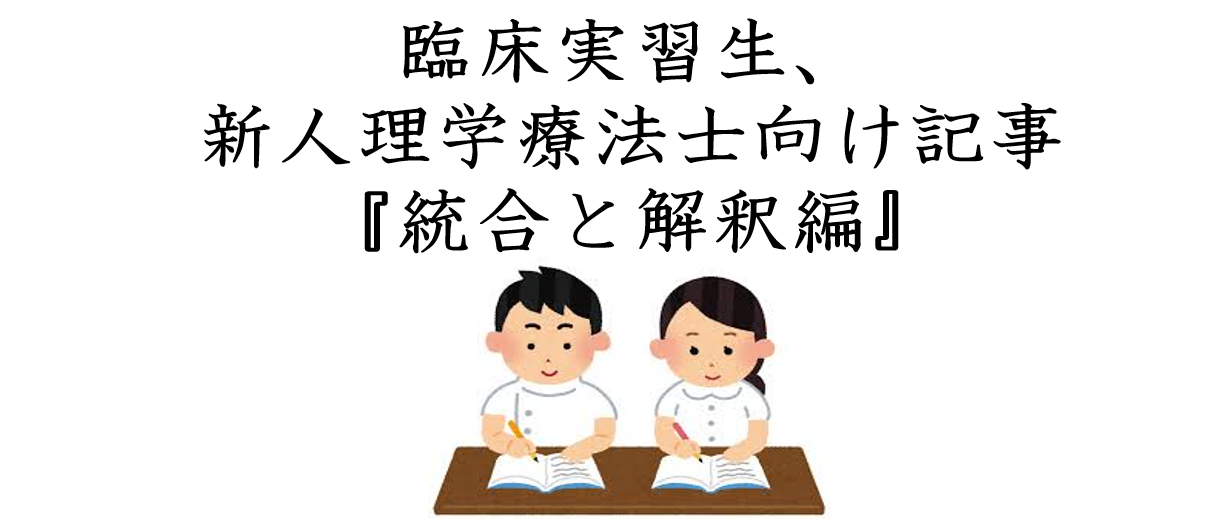
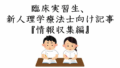
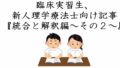
コメント