皆様こんにちは。
この記事は、理学療法士を目指す学生や新人理学療法士のために書いています。少しでも臨床のヒントが得られ、前向きなマインドで仕事に取り組んでもらうことを目指しています。
また、指導的立場にある理学療法士の先生にも役立てる内容をお伝えしたいと思いますので、併せて参考にして頂けたら幸いです。
さて、今回は情報収集のポイントについてです。
意外にこのことについて詳しく教えてもらう機会というのは、重要なことですが少ないのではないのでしょうか。
大事なことを最初にいうと、、、
1 情報収集の目的を理解すること
2 取得情報の優先度を決めておくこと
この2点がとても重要です☆
まず1の情報収集の目的はなんでしょうか?おそらく何個も出てくると思います。私が思う情報収集の目的は、一番はやはり「リスク管理」だと思います。診断名、現病歴、既往歴、病前のADL、性格、環境その他のパーソナルな情報等を把握しておくのは、土台にはリスク管理のためだと思います。
次に2の取得情報の優先度を決めておくというのは、何をカルテ情報から収集しなければならないのかのある程度【型】があるとよいでしょう。
私は主に次の項目を重要視していました。
※医師指示はマストのため省いています。
【年齢・性別】
【診断名】
【現病歴】
【既往歴】
【病前ADL】
【家屋環境・家族構成】
【利用サービス】
【介護度】
ですね。
私は病院勤務、老健勤務の経験からこの情報の優先度が高いことを学ぶことができました。主に在宅に復帰される患者様をイメージしてもらうと分かりやすいと思います。
かつ、上記の流れで説明口調で言葉にするだけでも、その人がイメージできると思いますので、読者の方は担当患者様を当てはめてやってみると良いでしょう。
私は新人育成においては、この情報集をアウトプットしてもらうことはとても重要視していました。結局のところ、うまくいかない理由がここにあることが多いので、漏れがないように指導をしていました。
これらの情報を収集することで、何が検討できるかというと、、、
どうしたら患者様の生活が成り立つか?
を検討できる材料になります。仮に情報という材料がなかったら、どう在宅へ安全に帰ってもらうのかの検討ができません。
特に【病前ADL】は重要で、その人の予後予測につながります。病前から生活動作に不安定性を認めている症例であれば、補助具の検討や最悪車いすも視野に入れなければならないため、環境の把握、マンパワーの把握等をしなければならないのです。
また、それに伴って【介護度】も重要になってきます。必要な介護サービスの枠は介護度によって決まっているため、どの程度の枠で在宅復帰後にサービスが受けられるのかもイメージしながらリハビリ診療にあたる必要があるのです。
でも、難しく考える必要はなくて、上記の項目を一つ一つ収集していければ、大きく方針が外れることはないと思います。
情報収集について理解が深められましたか?
言葉にすると意外とシンプルなのですが、その意味や目的について考えるきっかけはなかなかないと思います。この記事がそのきっかけになることを祈っております(^^♪
本日も最後まで読んでくださりありがとうございました☆
よりよい診療を目指して、お互い成長していきましょう(^^♪
本日の格言
患者様が安全に在宅復帰を果たせるかどうかは、情報収集にかかっている!!!
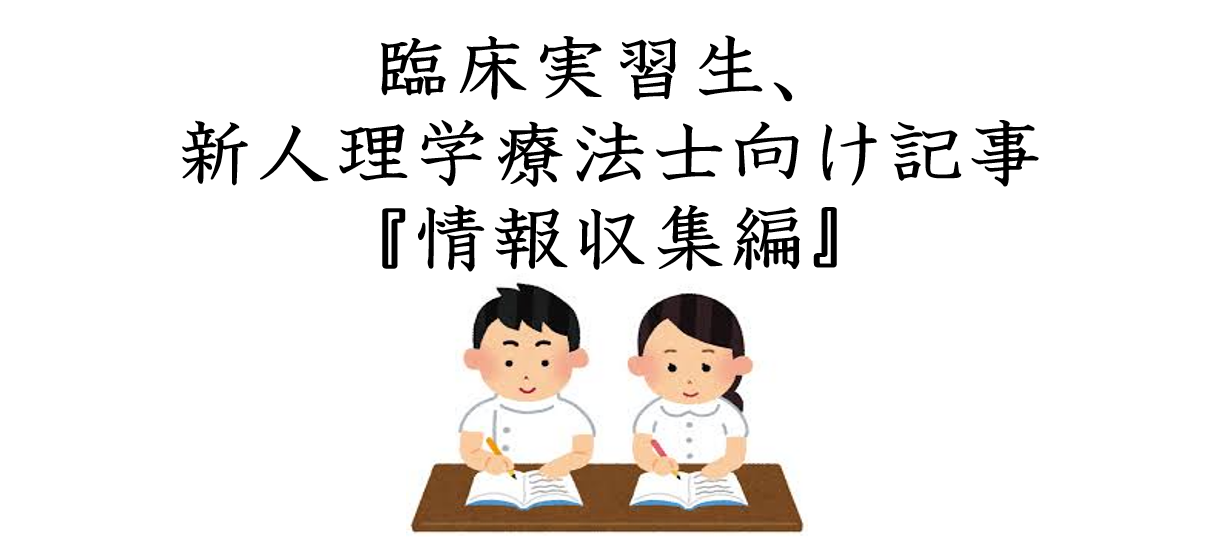
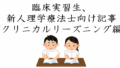
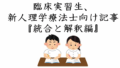
コメント