皆様こんにちは。
今回はタイトルの通り、人材採用と育成について自身の成功体験から、お伝えしたいと思います。
はじめに人材の採用というのは、どの企業でも上位の課題ではないかと思います。以前私自身が所属していた組織も、介護職さんやソーシャルワーカーさんの入れ替わりは激しかったですね。
そうした実情を反面教師と捉えて、どうしたら効果的に採用ができ、そして組織の戦力として職員を活かすかの勝ち筋は、めちゃくちゃ考えていました。その中で気付いたことは、入ってくる職員と受け入れる組織がwin-winの関係を構築することが一番だと思ったのです。
では、具体的にどうしたかというと、次の2点です。
1 インターンのように半日、または1日職場を体験してもらう
2 その職員の背景をきちんと考慮する
まず1について説明します。
このことについては、離職する原因を突き詰めた時に、こんなはずではなかったと入職者に思われないことが重要だと考えます。
そう思われてしまう原因としては、入る前段階で、施設見学や面接のみで終わらせてしまうことではないかと思います。その原因を摘み取る理由で、上に示したように、半日か1日職場を体験してもらうことが効果的です。その中で、曇りなき眼で見定めてもらえば良いのです。
職場の雰囲気はどうか
お客様への対応はどうか
休日のシフトはどうか
上司はやさしそうか(笑) などなど
見定めてもらった上で、その組織に入るか否かを決断してもらえば、良いかと思います。
人生一度きりですから、やっぱり思っていたのと違うなんてことが仮に起こってしまったら、お互いがロスですよね。そのロスを防ぐためには、入職する前段階の仕組みを整えると、その後が円滑に進み、お互いwin-winになることでしょう。
すべては事前準備ってことですよね(^^♪
次に2のその職員の背景をきちんと考慮するについて説明します。
その方の背景というのは、多く分けると2つに分類されると考えます。
それは、【職業人としての成長】か【家族環境の変化】です。
職業人としての成長については、そこに入って整形疾患を学びたいや老年期障害を学びたいなどの個々の成長願望と組織がマッチするかがポイントとなります。また、新人なのかどうかも重要なファクターです。
家族環境の変化については、子育て中なのか、または今後結婚・出産を考えているのか、両親の介護を必要としているのかなどの背景因子です。
仮に仕事が立て込んでしまったときに、そうした背景をきちんと把握してなかった場合に起こりうる弊害としては、無理矢理仕事をさせられたと誤解を生じさせてしまうことです。そうすると企業やその上司にデメリットが生じてしまいます。
家族環境が今こうだから、ある程度の就業時間の制限がある方としての認識があった上で入職という流れが理想的です。そうすることで、入職者も自分のことを配慮してもらっていてありがたいという気持ちが生まれ、長く働いてもらえる要因の一つになります。
この家族環境に配慮するということも、入職する前にすり合わせるという意味では、事前準備のたまものとして捉えると良いのではないかと思います。
入職者の成長願望や家族環境をくみ取る対応力というのは、組織側が持つべきではないかと思います。
効果的な採用についてまとめますと、
入る前が勝負
ということです!!
次に一般的な業務などを教育するときに効果的な方法についてお伝えしたいと思います。
大事なポイントは次の2つです。
1 その部署がどこを目指しているのかや上司の仕事における価値観をまずわかってもらうことに努める
2 プロセスが大事であるということを教え、成功体験を積ませる
まず、1について説明します。
このことについては、働く上での基軸を作るという表現に置き換えることができます。
私は介護老人保健施設でリハビリ科の主任を5年務めました。理学療法士というのは医療職であり、医療現場というのは、利用者様の命に関わる現場であるため、指導を蔑ろにするわけにはいきません。私は、新入職の人に対しては関わりの時間を毎日30分取っていました。利用者さんとのやりとりはどうだっかや難しく感じた点などを話し合いました。そうした中で、こういう時はこうした方が良いというアドバイスをしていきながら、上司の価値基準や判断基準を伝えていきます。私の根底にあったものは、「利用者様に寄り添った診療をすること」「励まし、傾聴を心がけること」でした。
こうした地道な積み重ねをした結果は、他部署からの評判が良くなりました。具体的には、リハビリの先生は優しいとか丁寧ですねという声を頂きました。
勘違いしてほしくないのは、ただ優しいとかではなくて、ちゃんと結果を出したうえでのこうした声でした。
いや~、ほんとにありがたかったですね(^^♪
反対に上司が適当になんの育成プランを持たずにやり過ごしていたらどうなっていたか。
おそらく、組織のメンバーがバラバラでなんのまとまりもない組織になっていたでしょう。組織のリーダーというのは、やはり頭の中で理想のビジョン・勝ち筋を描かないといけません。
次に2のプロセスが大事であるということを教え、成功体験を積ませるについて説明します。
これについては料理に例えると分かりやすいかと思います。例えば、肉じゃがを作るときに、ラッキーパンチでおいしくできた場合と試行錯誤しておいしく作れた場合、次に肉じゃがを作るときにどちらがまたおいしく作れるでしょうか?
別の言い方をするとおいしくできるという再現性が高いのはどちらでしょうか?
おそらく試行錯誤した方が再現性は高いと思います。天性の素質の持ち主は別としてね(^^♪。
そのため、結果にフォーカスするのではなくて、プロセスにフォーカスする指導を心掛けると良いでしょう。
リハビリの場面だと、患者さんが良くなったことを褒めるとき、「ただ良くなったね」と褒めるのではなく、例としては、、、
【〇〇くんは、この患者さんのことを小さなことでも、報告してくれて、私とその都度方向性の確認ができたから良くなったんだと思うよ。あとカンファレンスの申し送りも的確でわかりやすかったし、この学びを他の患者さんにも絶対活かせるから、頑張ってね。】
とプロセスに焦点をあてて褒めてあげると、部下の気付きにつながり非常に効果的です。部下の心理としては、自分としては当たり前のことで褒められるようなことだったのかなと捉える傾向があるため、あえて途中経過が良かったことを褒めることで、部下自身もプロセスの大事さを理解してくれます。
どうでしょう?
意外と褒めること一つにしても奥深いですよね(^^♪
ぜひ、読者の皆様もチャレンジしてみてください☆
◇まとめ
さて、今回は採用と教育について持論を述べました。はっきりいってしまえば、入れては辞め入れては辞めのサイクルでは時間とお金と心のロスが大きいと思います。
そうならないためには、入職する前段階で見定めること、マッチングしているかを検討すること、
そして、入職後は相手に寄り添ったフォローと教育をしていけば、自ずと良い組織は作られます!!
私もまさかここまで言語化できるなんて思ってもみませんでしたが、最初の頃はダメダメなマネジメントでしたから(;´∀`)
その中でなんとか這いつくばって学んで、成長していくもんです。
このブログが少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。
本日も最後まで読んでくださり、ありがとうございました。
本日の格言
管理職とは教育職

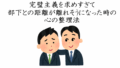
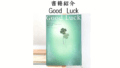
コメント